
転職先の企業が決まって、これから退職交渉に移ろうと思うんだ。
退職願を準備したんだけど渡すタイミングはいつが良いのかな?

それなら今回は退職願(退職届)を提出するタイミングについて紹介しよう。
転職活動が無事に終わり内定を貰ったら、後は退職交渉を行い会社を辞めるだけです。
会社に退職の意志を伝えて退職願(退職届)を提出すれば良いのですが「いつ提出すれば良いのか分からない」「タイミング次第では何か言われそうで怖い」と不安を持っている方も多くいます。
では、退職願(退職届)を提出するベストのタイミングはいつになるのでしょうか?
このページでは、退職を切り出すベストなタイミング、退職交渉の進め方、退職を行う上でのマナーや注意点について解説します。
- 内定から退職までの流れ
- 退職の意志を伝えるタイミング・マナー
- 退職願(退職届)の書き方・例文
- 引継ぎ作業、退職の挨拶について
転職の始め方、進め方についてはこちら
内定獲得から退職までの流れ

転職先の企業から内定を貰ったら、現在の会社を退職することになります。
「退職願(退職届)を出すだけで良いだろう。」と認識している人もいますが、その他にもやるべき事は多々あります。転職を成功させるためにも退職までの手順を確認しておきましょう。
退職交渉の大まかな流れについては以下の通りです。
- 直属の上司に相談する
- 退職願(退職届)を提出する
- 引継ぎ作業を行う
- お世話になった相手に挨拶
それぞれの過程については、以下で詳しく説明しているので参考になさってください。
退職交渉はアポイントメントから

まずは、退職の意思を上司に伝えるんだね。
なんて言えば良いのかな?

難しいことはないぞ。
話したいことがある旨を伝えれば良いんだ。
退職の意思を伝える際には、まず直属の上司にアポイントメントを取ります。
『〇〇部長、私の今後の事についてお話ししたいことがあります。お時間を頂けませんでしょうか。』と伝えて上司の都合の良いタイミングを聞きましょう。
アポを取る際の注意点として、上司に相談する前に他の社員や直属の上司以外に相談するのは避けるべきです。重要な話を伝えないことで上司の心証を悪くしてしまうと、転職に影響することがあります。
また、単に『お話があります。』と伝えるのもよくありません。『どうしたの?』と、その場で聞かれることになるので改まった言い回しを心がけましょう。
退職理由は自己都合が鉄則

上司の都合の良いタイミングを聞くことができたよ。
他に注意することがあれば教えてよ。

そうだな、退職理由を答える際には必ず自己都合にしておくことだ。
直属の上司にアポが取れたら、次は退職交渉に移ります。基本的に退職したい意思を伝えれば良いのですが、上司から転職する理由を尋ねられることがあります。
退職の理由を聞かれた際には『人間関係に不満がある』『労働環境が悪い』など会社に不満があった場合でも、自己都合であると答えましょう。
『この会社で続けていくことが難しい』など会社への不満を伝えることで、労働環境の改善を提案されて引き留めに会う可能性があります。
自己都合の退職理由の例としては『スキルアップを目指している』『〇〇業界でキャリアを築きたい』などがあります。会社に落ち度がったわけではなく、自分のために転職したい旨を伝えます。
しつこい引き止めにあった方は『しつこい引き止めで転職できない!会社を円満退職するための対処法とは』を参考になさってください。
退職願(退職届)を出すベストなタイミング

ところで、退職願(退職届)を提出するタイミングっていつになるのかな?

上司に相談するタイミングで渡せばよいぞ。
最低でも退職日の1ヵ月前に相談、提出ができれば良いな。
直属の上司に退職の意思を伝えたら、次は退職願(退職届)の提出になります。
ここで、退職願(退職届)を提出するタイミングについて確認しておきましょう。
結論から言うと、退職願(退職届)を提出するベストなタイミングは退職日の1〜2ヶ月前になります。 直属の上司に退職の意思を伝えて、そのまま退職願(退職届)を提出します。この時、繁忙期を避けて閑散期に報告できるとなお良いです。
法律では退職日の14日前に退職の意思を伝えることで退職が可能となりますが、急な退職は人員不足や引継ぎ作業の遅れで会社に迷惑をかけることになるため好ましくありません。
また、繁忙期に退職を切り出すことで「どうしてこのタイミングなんだ!」とまともに取り合ってもらえないことがあります。可能であれば、閑散期を狙って交渉を行いましょう。
退職願と退職届の違い
退職届と退職願は、似た意味で使われることがありますが明確な違いがあります。
退職願には「退職を希望します」という意思が込められるため、退職交渉のタイミングや自己都合退職で用いられます。
一方、退職届には「退職します」という意思が込められているため、退職願が受理されたタイミングや会社都合退職の場合に提出します。
上司にアポを取ってから提出する場合には、すでに退職することが決まっているようにも思われますが、退職の意志を会社に公表しているわけではないため退職願の方を提出します。
退職願(退職届)が受け入れられない時には退職代行に相談するのがおすすめです。
退職願(退職届)の書き方・例文

上司に退職の話が聞き入れられたよ。退職願を書こうと思うから書き方を教えて!

それなら退職願と退職届の書き方、例文について紹介しよう。
退職願や退職届を書く方に向けて、書き方や例文(横書き)を紹介します。
退職願(退職届)の書き方は上から順に次の様になります。
- 退職願(退職届)と記載
- 提出する日時を書く
- 会社の代表者名を書く
- 自身の部署と名前を記載
- 名前の横に捺印する
- 本文の前に『私事、』もしくは『私儀、』と書く
- 本文を書く
- 『以上』で締める
退職願の例文(横書き)
退職願
令和〇〇年〇月〇日
株式会社〇〇
代表取締役社長〇〇 殿
〇〇部〇〇課
(名前)印
私事、
このたび、一身上の都合により、来たる令和〇〇年〇月〇日をもって退職したく、ここにお願い申し上げます。
以上
退職届の例文(横書き)
退職届
令和△△年△月△日
株式会社△△
代表取締役社長△△ 殿
△△部△△課
(名前)印
私事、
このたび、一身上の都合により、来たる令和△△年△月△日をもって退職いたします。
以上
退職交渉が終わったら引継ぎ作業を行う

無事に退職交渉が終わったよ。
ここまで来れば転職も終わりだね!

いや、まだ引継ぎ作業が終わっていないだろう。
会社に迷惑をかけないためにもしっかり行っておこう。
退職願(退職届)を提出したら退職に向けて引継ぎ作業を行います。
残った仕事を片付けながら後任者に仕事の方法を伝えましょう。後任者が見つからない場合や引継ぎ作業が終わらない場合にはマニュアルを作成しておくことで、退職後に役立ちます。
マニュアルの作成は退職を妨害された際にも使えるので積極的に取り入れましょう。
また、取引先の企業やお得意様など、社外の人間に対して退職する旨を伝えましょう。後任者を紹介して感謝の意志を伝えます。
後任者を紹介するメールの例文
【件名】
転職のご報告(名前)
【本文】
株式会社〇〇 〇〇様
いつも大変お世話になっております。株式会社〇〇の(名前)です。
私事で大変恐縮ですが、一身上の都合により〇月〇日を最終出社日として退職することになりました。
〇〇様にはこれまで何かとお力添えをいただき、心より感謝しております。
本来であれば直接ご挨拶をすべきところ、メールでの挨拶になりましたことお詫び申し上げます。
後任は同部署の〇〇が務めさせていただきます。
後日改めて〇〇がご挨拶に伺いますので、変わらぬご指導の程よろしくお願い申し上げます。
最後になりましたが、貴社のご発展と〇〇様のますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。
(名前)
お世話になった相手に挨拶する

引継ぎ作業も終わったよ。
これで転職できるよね?

お世話になった方には挨拶しておこう。
直接の挨拶をメールを使い分けて挨拶するのが鉄則だ。
引継ぎ作業が終わり、退職日(最終出勤日)を迎えたらお世話になった方々に挨拶をします。『これまでお世話になった感謝』と『転職後にはこれまでの経験を活かして頑張っていく意思』を伝えましょう。
挨拶はメールで送れば良いのですが、直属の上司など特にお世話になった方には直接感謝を伝えるのがマナーとなっています。メールか直接にするかは相手によって変えてください。
退職の挨拶メール『社内向け』
【件名】
転職のご報告(名前)
【本文】
〇〇部〇〇課の皆様
お疲れ様です、〇〇部〇〇課の(名前)です。
この度、一身上の都合により本日〇月〇日を最終出社日として退職することになりました。
本来であれば直接ご挨拶をすべきところですが、メールでの挨拶にて失礼いたします。
在籍中はいたらぬ点も多々ありましたが、皆様に支えて頂き感謝しております。
この会社で培った経験を活かし、今後もより一層の精進をしてまいります。
私用連絡先は下記の通りになります。今後ともご連絡いただけると幸いです。
電話番号:
メール:
メールを送るタイミングやマナーを確認したい方は『転職時、退職時の挨拶メールの送り方|書き方やマナー、送るタイミング』を参考になさってください。
退職交渉のタイミング、退職願の書き方まとめ

このページでは、退職を控えている方のために退職の意思を伝えるベストなタイミングから退職交渉の進め方、退職願(退職届)の書き方・例文を紹介しました。
退職交渉を行うタイミングとしては、退職の1から2ヶ月前がベストとされます。また、繁忙期を避けて閑散期に相談するのが理想です。また、相談相手としては、必ず直属の上司を選びましょう。
退職交渉、引継ぎ作業が終われば転職もいよいよ終わりに近づきます。
無事に退職することができたら次の会社の入社に向けて準備をしましょう。
有給消化中にやることについては『転職の有給消化中にやること7選!入社に向けて有意義な時間を過ごそう』を参考になさってください。
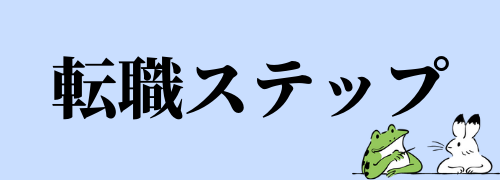






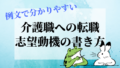
コメント